2024
May
8
NEW
-

Fashion
特集
目上の人に会うときは「ノーカラージャケット」がおすすめ!【3選】
2024.05.08
-

Model
武藤京子ブログ
パーカーはGU!デニムとの定番同士の組み合わせも更新を【モデルコーデ】
2024.05.08
-

Fashion
SNAP
【キラキラシューズ】で憂鬱な日も乗り越える!STORYライターの私物コーデ4選
2024.05.08
-

Lifestyle
特集
お義母さんへの母の日プレゼントには「夫婦円満の秘訣」も込められている?西尾由佳理アナが選ぶオススメギフト
2024.05.08
-

Fashion
今日の40代おしゃれコーデ
【甘ブラウス×辛口ジレ】脱・無難なネイビーコーデで保護者会へ
2024.05.08
-

Fashion
特集
人気コーデランキングトップ5! 4/21~30の「今日の40代おしゃれコーデ」
2024.05.07
-

Lifestyle
NEWS
Sponsored「キユーピー レモンドレッシング」がリニューアル!レモンの風味がさらにアップしました
2024.05.07
-

Beauty
特集
Sponsored「クレ・ド・ポー ボーテ」から宝石のような贅沢な色と質感のラグジュアリー ルージュ誕生
2024.05.07
-

Fashion
fromチームSTORY / SNAP
ピンクチュール、サンダルetc.STORYライターはアガるトレンドアイテムで連休明けのユーウツも吹き飛ばす!【コーデ3選】
2024.05.07
-

Fashion
特集
脱モノトーン!オフィスでも間違いのない「ピンク&ブルー」コーデ4選
2024.05.07
-

Fashion
特集
【デニムに、フレアスカートに】40代の最旬「ジレコーデ」3選
2024.05.07
-

Fashion
特集
40代でも取り入れられる「カラージャケット」に共通する特徴とは?【5選】
2024.05.07
PICK UP
Series
STORYweb 連載






































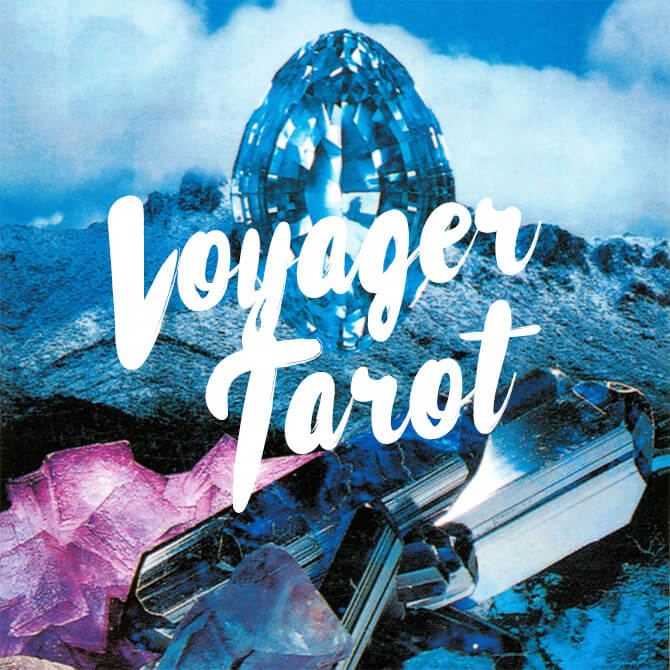










![【甘ニッシュは羽織りから!
コーデが気になる方はコメントに❤️ください!】
保存しておくと後から見返せます!
5月7日(火)
春の羽織りに多用するツーピースジャケットは
ドラマチックなスカートにもマッチします!
優雅な素材感、コンサバさんもチャレンジしやすい
端正なビッグフォルムでジャケット名品の呼び声が高い
「プルミエ アロンディスモン」。
トレンド問わず長く寄り添える名品は、
セット買いでの投資も間違いありません。
ドライなベージュとドラマチックな
赤スカートのカラートーンも大人っぽい仕上がりに❤️
ジャケット¥50,600
ジレ¥35,200(ともにプルミエ アロンディスモン)
スカート¥25,300(アルアバイル)
バッグ¥18,700(アンドミューク/アマン)
シューズ¥34,100(ピッピシック/ベイジュ)
イヤーカフ¥31,900(リューク)
※5月号P59掲載の商品です。お問い合わせはお控えください。
撮影/曽根将樹(PEACE MONKE)モデル/高垣麗子[身長:170cm] ヘア・メーク/陶山恵実 (ROI) スタイリスト/竹村はま子 取材/石川 恵
#甘ニッシュスタイル #甘ニッシュ #ツーピースジャケット #プルミエ アロンディスモン #40代コーデ #40代ファッション #ママファッション #大人カジュアル #50代ファッション #50代コーデ #トレンドコーデ](https://scontent-nrt1-2.cdninstagram.com/v/t39.30808-6/441933994_18435675361004568_5149421632796177233_n.jpg?_nc_cat=104&ccb=1-7&_nc_sid=18de74&_nc_ohc=OPPiUxj2HS0Q7kNvgFbw8fZ&_nc_ht=scontent-nrt1-2.cdninstagram.com&edm=ANo9K5cEAAAA&oh=00_AfB_pqeGL8IW6Fe4wZH_5vaFrxqE7txvZlSOEqmpA7iMog&oe=6640198C)
![【甘ニッシュに効くローファーが
気になる方はコメントに🤎ください!】
保存しておくと後から見返せます!
5月6日(月)
かっこよさを求めてきたけれど、
40代になってどこか可愛らしさのある
大人になりたいと思うようになったと潮田玲子さん。
今、求める凜々しさの中にある
女性らしさを名品をご紹介します💡
👞TOD’Sのローファー👞
潮田さん;
「ガンガン歩ける靴が好きな私にとって
ローファーは偏愛アイテムです。フォルムが美しくて
存在感のあるトッズのローファーはゴルフの
名門クラブでも自信を持って履けます!」
(シューズ左)
クラシカルなコイン。シューズ[H=2.5cm]¥152,900
(シューズ右)
シュー ズ[H=2.5cm]¥116,600(ともにトッズ/トッズ・ジャパン)
(着用)
シューズ「トッズ ケイト ローファー」[H=3.5cm] ¥127,600
バッグ¥306,900(ともにトッズ/トッズ・ジャパン)
肩に巻いたプルオーバー¥4,950(アングリッド)
スウェット¥23,100(ギャルリー・ヴィー /ギャルリー・ヴィー 丸の内店)
スカート¥8,800(スタイルミキサー/バロックジャパンリミテッド)
ピアス¥44,000(リューク)
靴下/スタイリスト私物
※5月号P82掲載の商品です。お問い合わせはお控えください。
撮影/谷田政史(CaNN)〈モデル〉、清藤直樹〈静物〉 モデル/潮田玲子[身長:166cm] ヘア・メーク/神戸春美 スタイリスト/竹村はま子 取材/小仲志帆
#潮田玲子 #トッズ #tods #ローファー #40代コーデ #40代ファッション #ママファッション #春コーデ #大人カジュアル #50代ファッション #50代コーデ #トレンドコーデ](https://scontent-nrt1-2.cdninstagram.com/v/t39.30808-6/441822811_18435497545004568_8083550341473774794_n.jpg?_nc_cat=110&ccb=1-7&_nc_sid=18de74&_nc_ohc=4pJsvA6DkDoQ7kNvgFRZPud&_nc_ht=scontent-nrt1-2.cdninstagram.com&edm=ANo9K5cEAAAA&oh=00_AfCL_Gd2TWqeOnQe_bII6EDbQk5_WpM9p1sgv34k3qRv_g&oe=66403E2E)
![【カーヴィーデニムが気になる!
と思ったらコメントに👖ください!】
保存しておくと後からコーデを見返せます!
5月5日(日)
この春大HITのカーヴィーデニムですが、
ハードルが高そうだと心配の方も多いかと思います。
でも穿くだけでこなれて見えて、
春の流行アイテムとも相性抜群なんです。
10年ほど前のデニム ブームのころ大好きだった
〝元カレ〟的なデニムブランド からも登場しているので、
迷ったら〝元サヤ〟もありですよ♡
< Photo1👖>
いい意味で飾り気のない色合いと、一度穿いたら虜になる
心地 よさはカーヴィーシルエットでも変わらず。
デニムパンツ¥ 47,300(マザー/リトルリーグ)
ジャケット¥ 116,600
ノースリーブカットソー¥19,800(ともにマディソンブルー)
バッグ¥35,200(TOMORROWLAND/TOMORROWLAND)
パンプス¥7,990(MANGO)
ピアス¥7,920(エティカ/ZUTTOHOLIC)
ブレスレット ¥11,000(イン ムード/フォー ティーン ショールーム)
リング¥14,300(ココシュニック オン キッチュ/ココシュニック)
< Photo2👖>
デニムパンツ¥39,600(ebure/ebure GINZA SIX店)
ブラウス¥24,200(ウィム ガゼット/ウィム ガゼット 玉川髙島屋S・C店)
Tシャツ¥20,900(バーロ スタジオ/ロン ハーマ ン)
バッグ¥68,200(ブリンク/THIRD MAGAZINE)
ローファー¥39,600(ファビオ ルスコーニ/ファビオ ルスコーニ ジェイアール名古屋タカシマヤ店)
イヤリング¥11,00(0 マージョ ベア/ココシュニック新宿タカシ
マヤ店)
ブレスレット¥13,200(ココシュニック オンキッチュ/ココシュニック)
< Photo3👖>
デニムパンツ¥9,900(Mila Owen)
ブラウス¥46,200(デザ
インワークス/デザインワークス 銀座店)
バッグ¥6,590(ZARA/ザラ カスタマーサービ ス)
パ ンプス¥34,100(ツル バイ マリコ オイカワ)
イヤリング¥8,100、ブレスレット¥10,290(ともにアビステ)
< Photo4👖>
デニムパンツ¥39,600(ロンハーマン ヴィンテージ/RHC ロンハーマ ン )
ニット¥20,900、カーディガ ン¥28,600(ともにロンハーマン/ロンハーマン)
バッグ¥47,300(ヘレンカミンスキー/ヘレンカミンスキー ギンザシック ス店)
サンダル¥39,600(ロランス/ザ・グランドインク)
サングラス¥50,600(モリー・スコット/モスコット トウキョウ)
ピアス¥19,140(ボヌール・ジュエリー/ZUTTO HOLIC)
< Photo5👖>
デニムパンツ¥47,300、ジャケット¥212,300、タンクトップ¥22,000(すべてマディソンブルー)
バッグ¥55,000(IACUCCI/ IACUCCI 大丸東京店)
スカーフ¥8,800(マニプリ)、パンプス¥23,100(オデット エオディール/オデット エ オディール 新宿店)
ピアス¥3,990(アビステ)
ブレスレット¥32,780(チビジュエルズ/チビジ ュエルズ・ジャパン)
※5月号P131掲載の商品です。お問い合わせはお控えください。
撮影/西崎博哉(MOUSTACHE)〈モデル〉坂根綾子〈静物〉
モデル/畑野ひろ子[身長:168cm] ヘア・メーク/TOMIE スタイリスト/MaiKo yoshida 取材/片山あゆみ
#カーヴィーデニム #デニム #40代コーデ #40代ファッション #ママファッション #大人カジュアル #50代ファッション #50代コーデ #トレンドコーデ](https://scontent-nrt1-2.cdninstagram.com/v/t39.30808-6/441420937_18435306772004568_5064205677564198129_n.jpg?_nc_cat=101&ccb=1-7&_nc_sid=18de74&_nc_ohc=UUwX3PxqCywQ7kNvgH-V4j9&_nc_ht=scontent-nrt1-2.cdninstagram.com&edm=ANo9K5cEAAAA&oh=00_AfDnYks8gMZ_SiQ0EzVW9KPnLw0-14YpFRdBUb0hVEXdlg&oe=66401DAA)
![【真のラグジュアリーバッグが
気になる方はコメントに🖤ください!】
保存しておくと記事を見返せます!
5月4日(土)
流行よりも時代を卓越した実用性を、
影響力よりは確立された自身のスタイルを
表現したいと思う真の富裕層から波及し始めた
「分かる人には分かるラグジュアリーさ」が
今やおしゃれのステータスシンボルの
主流になってきています!
自信を与えてくれ、これみよがしでないから
信頼感も得られ「初めまして」が多い春の
このシーズンにもぴったりです!
上
◆THE ROW◆
計算し尽くされた名品は
自分らしさが育まれるのも魅力
職人によるカッティングや縫製など
丁寧な手仕事は世界屈指の素材があって
より生きるものだと教えてくれるバッグ。
「SOFT MARGAUX 12」 バッグ[H23.5cm×W31.5cm×D19 cm]¥625,900(ザ・ロウ/ザ・ ロウ・ジャパン)
下
◆SAINT LAURENT◆
人生を左右する勝負の日にも手にできる
ベストバディ
手に取った人しかわからない実用性の高さを
ぜひ体験してほしい逸品。
「SMALL SAC DE JOUR BOWLING BAG」ストラップ付き バッグ[H16 cm×W31 cm×D10 cm]¥407,000(サンローラン バイ アンソニー・ヴァカレロ/サンロー ラン クライアントサービス)
※5月号P126掲載の商品です。
お問い合わせはお控えください。
撮影/佐藤 彩 スタイリスト/石関靖子 取材/小花有紀 構成/伊達敦子
#ラグジュアリーバッグ #therow #SAINTLAURENT #40代コーデ #40代ファッション #ママファッション #大人カジュアル #50代ファッション #50代コーデ #トレンドコーデ](https://scontent-nrt1-2.cdninstagram.com/v/t39.30808-6/441023644_18435104026004568_7531683959691737423_n.jpg?_nc_cat=108&ccb=1-7&_nc_sid=18de74&_nc_ohc=BIgJJF7r8K4Q7kNvgGCG_Zx&_nc_ht=scontent-nrt1-2.cdninstagram.com&edm=ANo9K5cEAAAA&oh=00_AfAduXcjTSs5IollRoftbtE9Ai3ATcHDBQJRr7fRybSLlA&oe=66400AC9)
![【カジュアル遠慮派が挑戦できる
スニーカーが気になる方は
コメントに🤎ください!】
保存しておくとコーデを後から見返せます!
5月3日(金)
普段のキレイめファッションにスニーカーは合わないと
パンプスやフラットシューズばかり
合わせていませんか…?
そんなカジュアル遠慮派でも挑戦できる
「微糖スニーカー」なファッションで
今っぽく更新できるんです!
<右から>
“華やぎビジューでエレガントさを加味”
👟Roger Vivier #rogervivier
キレイめ服×ビジュースニーカーが、
こなれ感を誘います。
パンプス合わせより断然今っぽい!
スニーカー¥174,900
バッグ¥567,600(ともにロジェ ヴィヴィエ/ロジェ・ヴィヴィエ・ジャパン)
ジレ¥31,900(プランクプロジェクト/プランクプロジェクト 青山店)
ニット¥30,800(ハイク/ボウルズ)
スカート¥38,500(ツル バイ マリコ オイカワ)
“アイコニックなメタルプレートで映える”
👟Sergio Rossi #sergiorossi
スリッポンスニーカーで苦手意識の克服を!
シルバーのスリッポンスニーカーで
キレイめな印象をキープ。
フロントのメタルプレートがピンクの甘さを程良く中和。
スニーカー¥118,800(セルジオ ロッシ/セルジオ ロッシ カスタマーサービス)
ドット柄ニット¥20,900(カデュネ)
パンツ¥26,400(エイチ ビューティー&ユース)
ピアス¥22,000
ブレスレット¥36,300(ともにブランイリス/ブラン イリス トーキョー)
”クリスタルストラップの煌めきで魅了 ”
👟JIMMY CHOO #JIMMYCHOO
前後2WAYで印象を変えて楽しんで!
前後に移動できるクリスタルを施したストラップが
今っぽく心ときめくモードに。
スニーカー¥145,200
バッグ¥311,300(ともにジミー チュウ)
トレンチジレ[袖付き]¥35,200(ザ ポーズ/ウィム ガゼット 玉川髙島屋店S・C)
カットソー¥14,300(アルアバイル)
デニムパンツ¥14,300(リーバイスR/SNIDEL ルミネ新宿2店)
ピアス¥63,800
リング¥39,600(ともにブランイリス/ブランイリス トーキョー)
※5月号P145掲載の商品です。お問合せはお控えください。
撮影/水野美隆 モデル/美香【身長:170cm】 ヘア・メーク/MAKI スタイリスト/井関かおり 取材/奥村千草 構成/伊達敦子
#スニーカー #大人のスニーカー #春コーデ #カラーコーデ #ピンクコーデ #40代コーデ #40代ファッション #ママファッション #大人カジュアル #50代ファッション #50代コーデ #トレンドコーデ](https://scontent-nrt1-2.cdninstagram.com/v/t39.30808-6/440895912_18434944768004568_5994521339287010902_n.jpg?_nc_cat=105&ccb=1-7&_nc_sid=18de74&_nc_ohc=9KeEokW6ZuoQ7kNvgHB8UB7&_nc_ht=scontent-nrt1-2.cdninstagram.com&edm=ANo9K5cEAAAA&oh=00_AfDKEvoyCfbBeb1Qdn-Ci1SmeKTu47qTRZIMI4dLYG0sHA&oe=664035FB)








![【甘いの苦手派の甘ニッシュアイテム
が気になる方はコメントに💙ください!】
保存しておくと後から見返せます!
4月25日(木)
誌面でおなじみの推しブランドからも
甘ニッシュアイテムが続々登場しています!
プロ目線で選り抜いたブランド名品を
STORYスタッフが熱くプレゼンします。
📣STORYスタッフ・リコメンド!📣
LE PHILのデニムセットアップ
媚びない甘ヘルシー×マスキュリン!
トレンド大全盛のデニム素材とベアトップ型の
オールインワンはこれからの季節の女子会にも
大活躍しそう!
デニムシャツ¥33,000
オールインワン¥36,300(ともにLE PHIL/LE PHIL NEWoMan 新宿店)
バッグ¥26,400(メアリ オルターナ/アダム エ ロペ)
サンダル¥38,500(PIPPI CHIC/ベイジュ)
ネックレス¥20,900(ローラロンバルディ/トゥモローランド)
リング¥29,700(Pearl for Life/ロードス)
※詳細は5月号P62の記事をご覧ください。
撮影/鏑木 穣(SIGNO) モデル/畑野ひろ子[身長:168cm] ヘア・メーク/KIKKU(Chrysanthemum) スタイリスト/井関かおり 取材/石川 恵、佐藤絵美子
#甘ニッシュ #デニムセットアップ #lephil #40代コーデ #40代ファッション #ママファッション #春コーデ #大人カジュアル #50代ファッション #50代コーデ #トレンドコーデ](https://scontent-nrt1-2.cdninstagram.com/v/t39.30808-6/440332886_18433487962004568_5596545347068200953_n.jpg?_nc_cat=108&ccb=1-7&_nc_sid=18de74&_nc_ohc=LbvWLkHwWpwQ7kNvgEsClZX&_nc_ht=scontent-nrt1-2.cdninstagram.com&edm=ANo9K5cEAAAA&oh=00_AfB9-2KJ2uaYcpV66LPzzKCC47CvmQClp2iFjrMOhMAF_A&oe=6640265F)
![【蛯原友里さんのピンクの着こなしが
気になる方はコメントに🩷ください!】
保存しておくとコーデを後から見返せます!
4月24日(水)
5月号では、蛯原友里さんが
“進化した自分を最も感じられるカラー”
ピンクをテーマに、NEW PINKスタイルをご紹介しています🩷
透明感も幸福感も纏えるピンクは、
実はエイジングを重ねた私たちの味方になってくれる色。
オシャレ経験値の高い大人だからこそ自信を持って、
この春は積極的に最愛ピンクを着てみましょう!
🩷New Pink Style 01
キャラ変の第一歩
“可愛いだけじゃない”ジャケットで
マニッシュに着てみたい!
「こんな風にピンクを着こなす心意気がかっこいい!
優しいトーンはシャープな縦のラインで
スタイリッシュに。コンバースで足元に抜け感を。
そんなトータルバランスが自分らしい」
スーツ¥319,000(Queen&Jack/エスティーム プレス)
ビスチェ¥30,800(LMND/サードマガジン)
バッグ¥137,500(ピエール アルディ/ピエール アルディ 東京)
スニーカー¥8,800(コンバース/コンバースインフォメーションセンター)
ピアス¥9,900(トゥデイフル/LIFE’s 代官山店)
🩷New Pink Style 02
着こなすことで自信!
インパクト大の青みピンクのパンツでモードスタイルに
POINT:
「どうせピンクを着るなら楽しんだもの勝ち!
ネオンのギンガムチェック×ボトムスは
ヴィヴィッドな青みピンクで潔く。
海外マダムのように堂々と大胆に着こなしたい!」
シャツ¥97,900(フォルテ フォルテ/コロネット)
パンツ¥55,000(アドーア)
バッグ¥14,850(メイド イン マダ/ジャック・オブ・ オール・トレーズ プレスルーム)
サンダル¥59,400(ネブローニ)
◆蛯原友里さんのリアルVOICE◆
「私とピンクの関係性」
以前はピンクといえば「可愛い」ものでしたが、
今は捉え方が変わってきました。ピンクって
可愛らしさや優しさだけじゃなく、モード感、
ハンサムさ、カッコ良さだって表現できる色。
歳を重ねてから身につけるピンクには、
そんな深みのあるパワーを感じるし、
それが自信につながる気がします!
ワードローブがベーシックになりがちな大人の今こそ、
好きに正直に、軽やかにピンクを取り入れたい🩷
※詳細は5月号P42から掲載を特集をご覧ください。
撮影/酒井貴生(aosora) モデル/蛯原友里[身長:168cm ] ヘア・メーク/paku☆chan スタイリスト/竹村はま子 取材/石川恵
#蛯原友里 #ピンクコーデ #ピンクスタイル #春コーデ #カラーコーデ #ピンクコーデ #40代コーデ #40代ファッション #ママファッション #大人カジュアル #50代ファッション #50代コーデ #トレンドコーデ](https://scontent-nrt1-2.cdninstagram.com/v/t39.30808-6/439504684_18433316632004568_7495238935399063904_n.jpg?_nc_cat=109&ccb=1-7&_nc_sid=18de74&_nc_ohc=ZVYN6rXp6qYQ7kNvgGKhN7Q&_nc_ht=scontent-nrt1-2.cdninstagram.com&edm=ANo9K5cEAAAA&oh=00_AfAPJZMyoLnE2KJKCUSv_IHcIRMAoRoeXTjEMJkbdq0Kaw&oe=66402759)
![【甘ニッシュコーデが気になる方は
コメントに💙ください!】
保存しておくと記事を見返せます!
4月23日(火)
発売中の5月号大特集の
2024年春の新スタイル、”甘ニッシュコーデ”。
華やかさ・信頼感・シーンレス
どれも手に入る最新コーデをご紹介します!
◆コンサバ派の鉄板!
“ツイードジャケット”は
ワントーンでキリリが気分◆
黒ビスチェを仕込んでキリッと感を後追い
インナーをワントーンにすることで縦長に
統一感が出せるのですらっと見えが叶います。
ジャケット¥37,400(カデュネ)
ビスチェ¥24,200(FRAY I.D/FRAY I.D ルミネ新宿2店)
ブラウス¥19,800(バビロン/バビロン新宿)
パンツ¥29,700(ロエフ/エイチ ビューティ&ユース)
バッグ¥20,900(マージシャ ーウッド/ユー バイ スピック&スパン ルミネ池袋店)
パンプス¥69,300(ペリーコ/アマン)
ネックレス¥26,400(マリアブラック×チノ/モールド)
※5月号P58掲載の記事です。お問い合わせはお控えください。
撮影/曽根将樹(PEACE MONKEY) モデル/高垣麗子[身長:170cm] ヘア・メーク/陶山恵実 (ROI) スタイリスト/竹村はま子 取材/石川 恵
#甘ニッシュ #ツイードジャケット #40代コーデ #40代ファッション #ママファッション #大人カジュアル #50代ファッション #50代コーデ #トレンドコーデ](https://scontent-nrt1-2.cdninstagram.com/v/t39.30808-6/439727058_18433140412004568_7213642611409101654_n.jpg?_nc_cat=102&ccb=1-7&_nc_sid=18de74&_nc_ohc=pYWPHnneBhgQ7kNvgHz_wXQ&_nc_ht=scontent-nrt1-2.cdninstagram.com&edm=ANo9K5cEAAAA&oh=00_AfDZCFrKbXv1IZ2Huy_IEk9RSA4iKz_C8__991EFjntNqw&oe=66400CB0)
![【春のピンクメイクが気になる方は、
コメントに💄ください!】
保存しておくと後から見返せます!
4月22日(月)
春のピンクメイクは、
圧倒的な透明感を引き立ててくれます🩷
指先には、柔らかさ、幸福感、ピュアでいて知的……。
そんなポジティブパワーが詰まった
ローズのリングたちを💍
💄メイクアップアーティスト
paku☆chan’s POINT!
「意志ある大人のピンクメイクが今また新鮮!
艶肌をベースに目元とリップにも ピンクを。
目元はPRADAのダイメンションズ マルチエフェクト アイメン ドウ04に
トープのアイラインで馴染ませます。
口元は 透明度の高いFujikoのノールックリップ02を」
リング右手小指¥29,700 左手薬指¥8,800(ともにマッソーズアンドマッソーズ/ショールーム ロイト)
右手中指¥143,000 左手人差し指¥303,600 左手中指¥132,000(すべてボロロ)
オフショルトップス¥9,900(プロヴォーク/ジャック・オブ・オール・ トレーズ プレスルーム)
※詳細は5月号P47の記事をご覧ください。
撮影/酒井貴生(aosora) モデル/蛯原友里[身長:168cm ] ヘア・メーク/paku☆chan スタイリスト/竹村はま子 取材/石川恵
#ピンクメイク #春メイク #トレンドメイク #蛯原友里](https://scontent-nrt1-2.cdninstagram.com/v/t39.30808-6/439613739_18432990052004568_2065810564275606088_n.jpg?_nc_cat=104&ccb=1-7&_nc_sid=18de74&_nc_ohc=v574YKhnJ64Q7kNvgFaLBPX&_nc_ht=scontent-nrt1-2.cdninstagram.com&edm=ANo9K5cEAAAA&oh=00_AfAqJNHLybWmmcPNEgswn2eHYwNLDFdQPxRfzFFIvsFP5Q&oe=664025BA)
![【キラキラシューズが
気になる方はコメントに👠ください!】
保存しておくと後からコーデを見返せます!
4月21日(日)
春モノトーンが好きだけれど、
パンチのある小物で変化をつけたい!
そんな時は、
馴染みすぎずきちんと主張できる、
メタリックやキラキラシューズが使い勝手抜群👠✨
今季旬のアクセサリーのような
遊びが利いた靴が、
効率重視のモノトーンコーデのマンネリ回避に有効です!
〈上から〉
メリージェーン[H8.5cm]¥207,900(ロジェ ヴィヴィエ/ロジェ・ヴィヴィエ・ジャパン)
サンダル[H10cm]¥169,400(セルジオ ロッシ/セルジオ ロッシ カスタマーサービス)
ミュール[H7cm]¥135,300
パンプス[H8.5cm]¥170,500(ともにジャンヴィト ロッシ/ジャンヴィト ロッシ ジャパン)
パンプス[H6.5cm]¥ 170,500(ジミー チュウ)
パンプス [H6.5cm]¥270,600(ロジェ ヴィヴィエ/ロジェ・ヴィヴィエ・ジャパン)
サンダル[H5cm]¥214,500(マノロブラニク/ブルーベル・ジャパン)
※詳細は5月号P98からの記事をご覧ください。
撮影/魚地武大(TENT)スタイリスト/石関靖子 取材/杉崎有宇子
#キラキラシューズ #40代ファッション #ママファッション #春コーデ #大人カジュアル #50代ファッション #50代コーデ#トレンドコーデ](https://scontent-nrt1-2.cdninstagram.com/v/t39.30808-6/438927554_18432775456004568_1695275738967829251_n.jpg?_nc_cat=105&ccb=1-7&_nc_sid=18de74&_nc_ohc=_t49f0LDDQUQ7kNvgGHoVhd&_nc_ht=scontent-nrt1-2.cdninstagram.com&edm=ANo9K5cEAAAA&oh=00_AfD4I7z-62AKwI_Xqc60eDHqpGevrS3NRZ32p8_T1PUuKw&oe=664010FC)
![【甘ニッシュの着こなしがしたい
という方はコメントに💙ください!】
保存しておくと後からコーデを見返せます!
4月20日(土)
発売中の5月号の大特集、甘ニッシュ✨
本日は、簡単にできて旬な
甘ニッシュスタイルのポイントをご紹介します!
<Point>
甘ブラウスにはマニッシュパンツを合わせて!
顔周りを華やかに盛り上げる甘ブラウスは
永遠の最愛アイテム。
キレイめテーパードから更新、
太パンツでエレガントなキレをプラスして!
大好きな甘ブラウスは、気負わないワイドパンツで
シックに着こなしたい。エレガントでいてかっこいい、
理想の女性像とオシャレがシンクロします。
パンツ¥42,900(サクラ/インターリブ)
ブラウス¥26,400(プルミエ アロンディスモン)
バッグ¥8,690 (バグマティ/フレームワーク ルミネ 新宿店)
シューズ¥49,500(ファビオ ルスコーニ/ファビオ ルスコーニ ジェイアール名古屋タカシマヤ店)
ピアス¥40,920(MAAYA)
※詳細は5月号P54〜の記事をご覧ください。
撮影/曽根将樹(PEACE MONKEY)〈モデル分〉、皆川哲矢〈静物〉 モデル/高垣麗子[身長:170cm] ヘア・メーク/陶山恵美 (ROI) スタイリスト/竹村はま子 取材/石川 恵
#甘ニッシュ #甘ブラウス #40代コーデ #40代ファッション #ママファッション #大人カジュアル #50代ファッション #50代コーデ #トレンドコーデ](https://scontent-nrt1-2.cdninstagram.com/v/t39.30808-6/438872623_18432592099004568_263156901209890321_n.jpg?_nc_cat=107&ccb=1-7&_nc_sid=18de74&_nc_ohc=SGkLVsSzgLAQ7kNvgFW8j3l&_nc_ht=scontent-nrt1-2.cdninstagram.com&edm=ANo9K5cEAAAA&oh=00_AfCkWYf-qFS9AkLw6uYMaTPwPdPWkUrp_Y4M2BZ9I2Uoyg&oe=66402041)
![【ガッチリ体型カバーコーデが
気になる方はコメントに💛ください!】
保存しておくと後から見返せます!
4月19日(金)
冬の間ずっと隠してきた体型を、
いきなり出すことになる春は、
どこか落ち着かないことも......。
そんな緊張感は、オシャレでカバーを✨
薄着でも体型をすっきり見せる春のトレンド服を
〝がっしり体型〟の潮田玲子さんセレクトで紹介します!
白よりのライトベージュは、
今季注目カラーのイエローとも相性抜群💛
ジャケット¥20,900(CELFORD/CELFORD ルミネ新宿1店)
カットソー¥25,300(オクト)
スカート¥52,800 (プルミエ アロンディスモン)
バッグ¥165,000(J&M デヴィッドソン /J&M デヴィッドソン カスタマーセンター)
パンプス¥86,900(ペリーコ/アマン)
ピアス¥46,200(ブランイリス/ブランイリス トーキョー)
撮影/曽根将樹(PEACE MONKEY) モデル/潮田玲子[身長:166cm] ヘア・メーク/森 ユキオ(ROI) スタイリスト/井関かおり 取材/澁谷真紀子
#潮田玲子 #がっしり体型 #40代コーデ #40代ファッション #ママファッション #春コーデ #大人カジュアル #50代ファッション #50代コーデ #トレンドコーデ](https://scontent-nrt1-2.cdninstagram.com/v/t39.30808-6/438903353_18432404188004568_4428014544253041550_n.jpg?_nc_cat=107&ccb=1-7&_nc_sid=18de74&_nc_ohc=kA2I4hKEIPgQ7kNvgHLUO05&_nc_oc=Adgf5iWeNoe9XV5Bufd5YDXDl992FbcDtoI1IXe2Q6lBDrrsEnNPIyyxWCQsKnNZSLI&_nc_ht=scontent-nrt1-2.cdninstagram.com&edm=ANo9K5cEAAAA&oh=00_AfCBY_htriHYrkG5Y-LTHjhFQYahNT7-imjUF3Q2C1Dyxw&oe=664032A9)