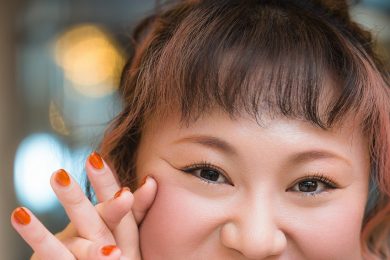「4歳の娘たちに、私の死をどう伝えたらいいですか?」
若くしてがんになった母親は、こう語ったという――。
その母親はみどりさん、32歳。病名はスキルス胃がん。ステージ4。双子の娘はまだ4歳。
がんと診断され、最期を迎えるまでに、母親と家族は、何をどう選択したのか。何に悩み、どう生きたのか。そして、母親が娘たちに残した2冊のノートには、何が書かれていたのか。
若いがん患者と家族、医療者たちの実像を描き、在宅医療の現実にも迫る感動のノンフィクション『2冊のだいすきノート』(田村建二著、光文社)から、著者の思いのこめられた「はじめに」を公開します。

2021年の5月15日。横浜市にある一軒家の2階リビングで、私はこの日初めて会う男性と、ご自宅のテーブルを挟んで向かい合っていました。
新型コロナウイルス感染症の「第4波」が続いていました。リビングの窓は換気も兼ねて開け放たれ、陽光をはらんだ春の空気がゆっくりと部屋の中を流れていました。
マスクをつけた私は、やはりマスク姿の男性に言いました。
「夢の中で、どうして笑っておられたのか、そのわけを知りたいんです」
男性の名は、こうめいさん。1年4カ月足らず前に妻を亡くしていました。
互いにマスクで表情がよく見えないなか、いまの言葉で取材の趣旨がちゃんと伝わっているかな。そんなふうに思っていたら、視線を少しそらしたこうめいさんの両目がじんわりと潤んでいくのに気づきました。
こうめいさんにとって、妻の死はまだ、記憶のすぐそばにありました。あせらず、慎重にお話を聞いていこうと、私は決めました。
32歳という若さでがんと闘った母親の笑顔のわけを探して
この本は、32歳という若さ、しかも4歳の双子の娘をもつ女性が、治療が最も難しいタイプのがんと診断されてから最期を迎えるまでに、どんな選択をし、どう生きたのか、そし、夫や娘をはじめとした家族は何に迷い、悩み、どう行動したのかをつづった物語です。女性の名は、みどりさん。こうめいさんの妻です。
朝日新聞の朝刊紙面およびデジタル版にて2021年秋に連載した「患者を生きる 娘たちへ 2冊のだいすきノート」での記事を出発点に、ご家族や医療関係者に改めて取材して、大幅に加筆、というか、全面的と言っていいほど書き直す形になりました。今回の取材のきっかけは、たかこさんという女性とのかかわりを通じてでした。たかこさんは20代のときに白血病を発症し、お母さまからの骨髄移植によって命を救われました。私は朝日新聞社でずっと医療・医学分野を担当していて、たかこさんは、12年ほど前からの取材先のお一人でした。2020年3月、そのたかこさんが朝日新聞に寄せてくれた投稿記事を通じて、32歳の義理の姪を少し前にがんで亡くされたことを知りました。その姪が、みどりさんでした。
当時、私は世界中に猛烈な勢いで広がり始めていた新型コロナ感染症の取材に日々追われ、しかも東京から大阪への転勤を目前に控えていて、たかこさんにすぐ、連絡をとることはできませんでした。ただ、次のことが強く印象に残っていました。
たかこさんによれば、葬儀を終えた直後の朝、みどりさんの娘たちが、「ママが立って笑っている夢を見た」
と、にこやかに言ったというのです。
そんなこと、ありえるのか?と思いました。
まず、葬儀を終えたばかりということは、娘たちにとって、最愛であることはもちろん、自分たちを守ってくれる最大の存在である母親を亡くした直後です。4歳とはいえ、深い悲しみ、さびしさに浸っていたとしてもまったくおかしくありません。どうして、娘たちは「にこやか」でいられたのか。
次に、夢の中でママが「笑っていた」ということ。
娘たちが「笑顔のママ」として記憶していたということは、それだけたくさんの笑顔を、みどりさんは娘たちに見せていたに違いありません。
ただ、がんで亡くなった人は少なからず、いずれかの段階で痛みに見舞われます。私の母は18年あまり前に大腸がんで亡くなりましたが、治療目的での入院中、対処が十分になされないまま、痛みに苦しみ続けていたことを鮮明に覚えています。
そのころから比べれば、最近は痛みを和らげる緩和医療はずいぶん進歩してきました。とはいえ、がん患者のすべての痛みが克服できたとは、とてもいえないのが現実です。
がんの緩和ケアについて取材し、いまでも多くの患者が取り除ききれない痛みに苦しんでいることを感じ、何度か記事にも書いてきました。みどりさんがもし、いつも痛みに苦しんでいたなら、子どもたちに「笑顔のママ」として記憶されることはなかったはずです。
みどりさんの痛みはどうだったのか。痛みがあったとしたら、どんな緩和ケアを受けていたのか、知りたいと思いました。
痛みを抑えるだけでは足りません。
もし、ずっと病院に入院していて、一緒に過ごすことがほとんどかなわなければ、やはり「笑顔のママ」という印象は残りにくいでしょう。
たかこさんによれば、みどりさんは最期のときを自宅で迎えたそうでした。がんの患者が自宅で亡くなるケースも最近はたしかに増えています。とはいえ、32歳という若い患者の事例はさほど多くないはずです。最期まで在宅ですごせるために、いったいどんな環境があったのか。
そして、みどりさんが娘たちに笑顔を見せられるようにするため、家族や医療スタッフたちによる、いろいろなサポートがあったのだろうと予想しました。それらを知りたいと思いました。
がんで旅立った母親が、2人の娘に残した2冊のノートとは

2021年の春、私は偶然にも、大阪から再び東京に転勤することになりました。この物語に登場するみなさんはほぼ、首都圏在住です。私はたかこさんに、夫のこうめいさんを紹介してもらい、同意をいただいて取材を始めました。そして、コロナ取材の合間をぬってお話を聞いていく中で、みどりさんが2人の娘へのメッセージをつづった「だいすきノート」を残されていたことを知りました。
小さな子をもつ親が、きっと治ることのない重い病気であることがわかったとき、子どもたちにその病気について伝えるのか、伝えるとしたら、どのようにするのか。自身の「死」についてはどうか。その問いは、この物語の最大のテーマとなりました。
ですが、私が当初、一番知りたかったのは、みどりさんがどのようにして、娘たちに「笑顔のママ」の記憶を残すことができたのか、でした。そして、「2人への言葉をつづったノートは、どのようにして書かれるにいたったのか」という疑問が加わりました。
取材が始まったとき、私は仕事用パソコンのデスクトップに「ママは笑ってる」という名前のフォルダをつくりました。この時点で考えた、連載記事の仮のタイトル案でした。そして、そのフォルダに、取材メモや提供いただいた写真データ、関連する医学文献や医療・介護制度などの資料を収めていきました。
文中の記述はすべて、取材で知った事実にもとづいています。ただ、娘2人がまだ小さいため、フルネームではなく「もっちゃん」、「こっちゃん」と愛称にとどめ、2人の実名を呼んだ登場人物の言葉や文面の記載は愛称に変えました。またそれに合わせて、ご家族の氏名も姓は省き、名前をひらがなで記載する形にしました。
巻頭の写真も、「現在の」もっちゃん、こっちゃんの顔が容易に推測できるような、正面からの顔を載せるのは最小限にとどめています。2人は今回、喜んで取材に協力してくれていますが(ときどき、〝えーまた来たのー?〟と疎まれることもありますが)、大きくなったとき、現在の気持ちが変わらないとも限らないからです。
生命科学について取材していると、「これまで、ほかの研究者にはできなかったのに、どうしてこの人には新しい発見ができたのか、新たな成果を生み出せたのか」と疑問に思うことが少なくありません。
2003年5月、私は奈良先端科学技術大学院大学で開かれたとある記者会見に出席しました。発表者は、当時この大学の助教授だった山中伸弥さんでした。再生医学にかかわる大きな研究成果が2本、それぞれ世界的に著名な科学誌に同時期に掲載される、という趣旨の会見でした。
ここでも私は、「なぜ、ほかの人にできなかったのに、あなたにはできたのですか」と質問したことを覚えています。山中さんはその後、京都大学に移り、ノーベル賞の受賞につながるiPS細胞の樹立を報告することになります。
私にとって今回の取材は、「みどりさんという女性はどうして、娘たちに笑顔の記憶と言葉(ノート)を残すことができたのか」という疑問を解くための、みどりさんと家族の道のりをたどり、記録する旅でもありました。その軌跡を、読者のみなさんにも最後までたどっていただけたなら、記者としてこれ以上の喜びはありません。

『2冊のだいすきノート ~32歳、がんで旅立ったママが、4歳の双子に残した笑顔と言葉』光文社刊(Amazonのサイトへ)